人口減少や交通インフラの課題を抱える離島地域では、持続的な地域社会の維持が重要な課題です。特に、若者の都市部への流出が進む中、離島での起業を促進することで雇用の創出や定住促進が期待されています。
こうした背景のもと、国は「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」や利子補給制度など、離島での創業や事業拡大を支援する制度を整備しています。離島で起業したい方にとっては、最大で費用負担の3/4を軽減できる可能性があるので、活用したい制度です。
この記事では、離島起業を支援する補助金制度の仕組みや活用事例について解説します。
目次
起業すると補助金の対象となる「特定有人国境離島」とは
特定有人国境離島とは、日本の国境に位置する離島のうち、住民の継続的な居住を維持することが国家的に重要とされる、法律で指定された地域のことです。全国で15地域71島が指定を受けています。これらの離島は、漁業や海洋調査、領海警備などの拠点として戦略的な役割を担っています。
しかし、離島では人口減少の進行や地理的孤立などにより、無人化のリスクが高まっている点が課題となっています。一度無人化してしまうと、領海の保全や国境管理といった機能を再び構築することは困難であるため、持続的な人の居住と地域社会の維持が必要です。
このような背景から、国は特定有人国境離島に対して、インフラ整備や公共機関の設置、港湾の補強、さらには民間事業者による地域経済の活性化に向けた支援を行っています。
離島での起業で使える「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」
「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」は、離島における雇用の創出や定住促進を目的として、起業や事業拡大を行う民間事業者に対して事業資金の一部を補助する制度です。地域活性化と、持続可能な社会の形成を支援するために、2025年は40億円の交付が予定されています。
出典:内閣府「令和7年度 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 交付決定内訳」
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金は、単純に企業誘致を行うだけでなく、その企業が離島に根付いて地域振興に成功するように、事業の継続を支援する制度です。地方創生や地域コミュニティの再生に関心を持つ方にとって、有効な支援策の1つと言えます。
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の要件
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の交付対象になるのは、主に以下の4つの取り組みです。
○運賃低廉化
本土と特定有人国境離島地域を結ぶ離島住民向けの航路についてJR運賃並、航空路について新幹線運賃並の引き下げを支援する。
○物資の費用負担の軽減
特定有人国境離島地域における事業の継続、事業拡大等を図るため、農水産品(生鮮)などに係る輸送コストの低廉化を支援する。
○雇用機会の拡充
民間事業者等による創業・事業拡大を行う事業資金等を支援する。
○観光振興
滞在プラン等の企画・開発、宣伝・実証、販売促進による旅行者の費用負担の軽減の取組などを支援する。
出典:内閣府「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業について」
これらに沿った事業を、ビジネスアイデアレベルではなく事業計画のレベルで考案し、収益性や実現可能性が十分なことを証明しなければ補助金は交付されません。
以下では、八丈町での特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の要件を参考に、詳細な交付要件について解説します。
補助対象者
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の補助対象者となるのは、以下の要件を満たした特定有人国境離島地域で対価を得て事業を行う個人または法人です。
- 特定有人国境離島地域で新たに創業をする方
- すでに特定有人国境離島地域内で事業を営んでおり、事業拡大を行う方
創業とは新規に開業・会社設立する場合だけでなく、事業承継により既存事業を引き継ぐ場合も含まれます。また、地域への定住を促進する狙いもあるので、U・I・Jターン移住者や地域おこし協力隊の卒業者も対象になります。
事業に関する要件
交付金を受けるための事業要件は、以下の通りです。
- 雇用の創出が見込まれ、助成期間終了後も雇用が継続または拡大すると予測できる
- 売上高や付加価値額の増加が助成期間終了後にも継続すると見込まれる
- 創業や事業拡大に必要な資金を、自己資金または金融機関からの融資などで十分に調達できる
また、単なる設備の更新やビジネスモデルが不明確な事業は対象外です。公共団体や行政が行うべき事業、ほかの補助金・助成金などを前提とした事業も支援の対象外となります。
加えて、事業内容が交付金の趣旨に沿った以下のようなものである必要があります。
- 島外の需要を取り込み、島内の経済および雇用を拡大させる事業
- 島内の生活や産業にとって必要不可欠な商品・サービスで、かつ離島地域であることによって生じている不利を改善する事業
- 島への転入者数の増加に直接的に効果があることが明確な事業
- 島内に働き手を呼び込む、または安定的な雇用を創出する効果がある事業
- 訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備を伴う事業
地域産業として離島に根付き、雇用創出につながり、地域社会の課題を解決する事業でなければ、補助金は交付されません。
雇用に関する要件
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金は、雇用の創出を重視している性質上、以下のような雇用要件を満たす必要があります。
- 計画期間中に、週の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画終了後も継続して雇用する
- 補助金助成終了後も、雇用が継続または拡大することを示す目的で賃金台帳や雇用保険加入状況の監査を受ける
- 退職や解雇が発生した場合は、速やかに新たな人材を雇用する
従業員が事業期間終了後すぐに解雇されるような計画は、交付対象外となりますので注意しましょう。
なお、離島に移住して新たに起業する場合、自らを新規雇用と見なすことも可能です。また、季節的な営業休止期間がある場合、その期間は雇用継続期間から除くことができます。
補助対象の経費と上限額
補助金が対象となる経費項目と各上限額は以下の通りです。
| 設備費(減価償却費含む) | 機械、器具、備品の購入・設置費用、リース・レンタル料 (※個人資産となる不動産や自家用車、汎用性が高いPCやスマホなどは対象外) |
|---|---|
| 改修費(減価償却費含む) | 事業に必要な建物や設備の改修費(単なる老朽化対策は対象外) |
| 広告宣伝費 | 広告掲載費用やホームページ、パンフレット、DM制作・配布費用 |
| 店舗等借入費 | 事業用の店舗や事務所賃料 |
| 人件費 | 新規雇用従業員の給与 常勤:月額35万円、非常勤:月額20万円、パート・アルバイト:日額8,000円まで |
| 研究開発費 | 市場調査や試作品製作の経費、外注費など |
| 島外からの事務所移転費 | 離島外から離島へ事務所を移転する際の引越費用 |
補助を受ける際には、事業との関連性が明確で、かつ支出を証明できる書類があることが条件です。また、国や地方自治体の他の補助事業の対象経費と重複する場合は対象外となります。
補助金額の上限は以下の通りです。
| 区分 | 補助対象事業費の上限額(自己負担額) |
|---|---|
| 創業 | 最大600万円(150万円) |
| 事業拡大(設備投資を伴う場合) | 最大1,600万円(400万円) |
| 事業拡大(設備投資を伴わない場合) | 最大1,200万円(300万円) |
「設備投資を伴わない事業拡大」とは、設備費や改修費を含まない形での事業拡大を指します。なお、補助金の交付にあたっては、1/4以上の自己負担が必須であり、自己資金あるいは金融機関などから調達が必要です。
離島で起業する際に役立つ利子補給制度
特定有人国境離島では、創業・事業拡大のための資金調達が本土に比べて難しく、起業家の負担が大きくなりがちです。こうした課題を解消するため、地域の金融機関を通じた融資に対し、国が利子補給を行う「特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金」制度が設けられています。
特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金は、雇用機会拡充事業に採択された事業者が対象です。補助金の支払いは設備設置などが完了した後となるため、事前の資金繰りが必要になりますが、この制度を活用すれば、最大7,200万円の融資について、最長5年間の利子補給を受けることが可能です。
離島での起業の成功事例
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した起業事例には、以下のようなものがあります。いずれも地域資源を活用したり、社会課題に対応したりしながら新たな雇用を創出し、地域経済の活性化に貢献できた事例です。
| 三宅島 |
|---|
|
三宅島では、個人事業主である西野農園が、地元特産品の明日葉やレモンを活用した新商品開発に着手しました。交付金は、研究開発費、広告宣伝費、ネット販売促進のための費用、さらに雇用者の人件費に充てられました。 取り組みにより、商品ラインアップの多様化が進み、消費者ニーズへの柔軟な対応が可能となりました。また、ネット販売の強化によって販路を全国へと広げることに成功し、島内外からの注文が増加しました。令和5年3月末時点で3名の新たな雇用が実現しており、地域の雇用拡充にも寄与しています。 |
| 対馬 |
|---|
|
対馬では、高齢者をはじめとする買い物困難者を支援する移動販売事業が展開されています。対馬北部の買い物環境が乏しい地域に向けて、移動販売車両と専用システムを導入し、地域住民が安心して暮らせる生活基盤を整備しました。 補助金は、販売車両の導入費用やシステム整備費、新規雇用者の人件費などに活用されました。令和3年度には2台の移動販売車を導入し、令和5年度にはさらに1台が追加される予定です。事業開始以降、2名の雇用が実現し、知人紹介やハローワークを通じて人材確保が行われました。 |
まとめ
離島での起業は、地域の活性化や新たな雇用の創出につながる重要な取り組みです。「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」や利子補給制度を活用すれば、設備費や人件費、広告費などの負担を大きく軽減できます。
三宅島や対馬での事例からも分かるように、地域課題と結びついたビジネスには確かな需要があり、補助金の支援を受けながら成功に導くことが可能です。ただし、補助対象となるには明確な雇用計画や事業目的が求められるため、事前準備と制度の理解が不可欠です。




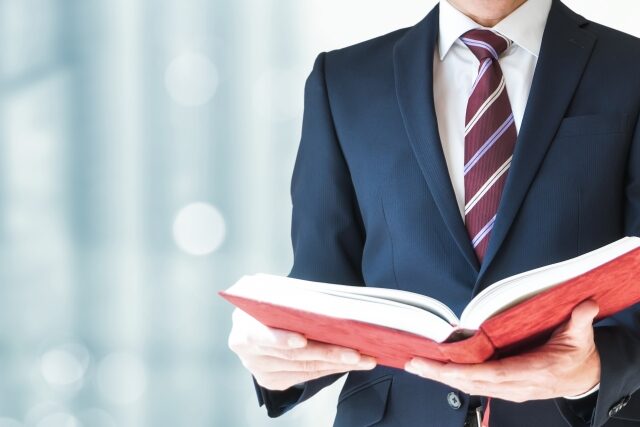






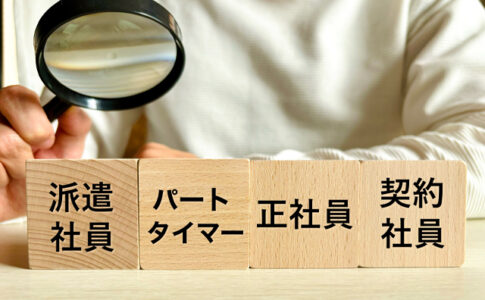







コメントを残す