労働基準法は、労働時間・賃金・休日・休暇など、労働者の権利を守るための最低基準を定めている法律です。働き手として、労働基準法の内容を大まかにでも知っておかないと、自分の権利が侵害されていることに気づかず、適切な対応ができないリスクがあります。
労働基準法に違反する不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談したり、法的手段をとったりすることが可能です。
当記事では、労働基準法とは何かといった基礎的な内容から、労働基準法の主な規定まで、分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
労働基準法とは?
労働基準法は、日本の労働法において中心的な役割を果たす法律です。労働者の最低限の労働条件を保障し、権利を守り、安全で健康的な労働環境を確保することを目的としています。
労働基準法は、労働者だけでなく、企業にとっても重要な法律です。企業は、社会の一員として、法令を遵守し、倫理的な行動をとる責任があります。労働基準法に違反した場合、企業は行政処分や罰金などの法的制裁を受ける可能性や、労働者からの訴訟や損害賠償請求のリスクも高まります。
労働基準法の基本概要
労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律です。労働基準法はあらゆる雇用形態の労働者に適用され、使用者に労働条件の最低基準を守ることを義務付けています。法違反には罰則もありますので、事業者はこの法律を遵守しなければなりません。
【主な内容】
- 労働時間の規制(原則1日8時間、週40時間)
- 休憩時間の確保
- 深夜労働の制限
- 年次有給休暇の確保
- 安全衛生の確保
- 労働条件の明示
- 解雇の制限
- 賃金の適正な支払い
- 男女同一賃金の原則
労働基準法は、労働者と使用者間の力関係の不均衡を是正し、安心して働ける環境を整備するための重要な法律です。
労働基準法の対象者は?
労働基準法の対象者は、原則として日本国内で事業または事務所に使用されて賃金を支払われるすべての労働者です。雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)や職種は問われません。
ただし、フリーランスや業務委託、請負労働者などは、労働基準法の保護対象となる「労働者」ではありません。理由としては、これらの形態で働く人は、労働契約上の従属関係にないためです。しかし、事業者との間に従属関係のような実態がある場合は、保護の対象となる可能性があります。
一部の業種や職種については、労働基準法の適用が限定されることもあります。例えば、農業や畜産業に従事する人は、「労働時間」や「割増賃金」などの規定において一部適用外です。さらに、家族経営の事業で同居する親族のみを雇う場合や、特定の公務員(特別職の地方公務員など)、一部の船員、家事使用人などは、労働基準法の保護を受けません。これらの例外条件は、具体的な労働環境や雇用の性質に基づいて決定されています。
労働基準法の主な規定
労働基準法の主な規定として、厚生労働省「労働基準法のポイント」では以下の項目が挙げられています。
- 労働条件の明示
- 就業規則
- 労働時間、休憩・休日
- 年次有給休暇
- 賃金
- 労働者名簿、賃金台帳
- 解雇・雇止め
- その他の労働条件
- 健康の確保
以下では、厚生労働省「労働基準法のポイント」を基に、上記の中から確認しておきたい基本的なものについて解説します。
労働契約の明示
「労働契約の明示」は、雇用関係の透明性と労働者の権利保護を目的としています。具体的には、労働基準法第15条に基づき、雇用主は労働者を雇い入れた際に、労働条件を書面で明示する義務があります。明示すべき労働条件は、労働契約の期間、就業場所、従事する業務の内容、労働時間(始業・終業時刻、休憩、休日、時間外労働の有無)、賃金の計算方法と支払い時期、退職に関する事項(解雇の条件を含む)などです。
出典:e-GOV 法令検索「労働基準法 第十五条(労働条件の明示)」
さらに、昇給や退職手当、賞与など、企業の具体的な制度に関する情報も書面で交付することが推奨されています。有期労働契約を結ぶ場合は、労働契約の更新に関する可能性やその基準の明示も必要です。これにより、労働契約の更新や終了の基準が労働者に事前に理解され、労働環境の公平性が維持されます。
労働時間・残業
「労働時間・残業」の規定は、労働者の健康保護と公平な労働環境の確保のための規定です。
法定の基本労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。これを超える労働を行う場合、使用者は「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定)を労働者代表と締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。36協定は、時間外労働の限度を定めるものであり、適切な労働時間管理を求めています。
また、休憩と休日に関する規定もあり、使用者は労働者に対して1週間に少なくとも1回、または4週間に4日以上の休日を与えなくてはなりません。このような規定により、長時間労働の防止と労働者の健康維持が促進されます。
出典:e-GOV 法令検索「労働基準法 第三十五条(休日)」
しかし実態としては、時間外労働が適正に管理されておらず、不適切な労働時間の自己申告や長時間労働が問題となるケースも見られます。使用者は適切な時間管理を徹底し、必要に応じて労働者の自己申告の適正性を確認し、労働時間の実態に合致するよう努めなくてはなりません。
休日・有給休暇
使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える義務があります。また、前述の通り、少なくとも毎週1日の休日または4週間に4日以上の休日を提供しなければなりません。
年次有給休暇についても明確な規定が設けられています。雇用から6か月経過し、所定労働日の80%以上に出勤した労働者は、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数に応じて付与日数が増える(6年6か月以上まで)仕組みです。
出典:e-GOV 法令検索「労働基準法 第三十九条(年次有給休暇)」
年次有給休暇は、法律により発生する権利であり、労働者が請求することで使用できます。ただし、使用者は事業の運営に支障が出る場合に限り、休暇の時季を変更する権利を持ちます。
年次有給休暇の取得は、原則として1日単位ですが、半日または時間単位での取得が可能です。また、法改正により、年10日以上の休暇が付与される労働者は、使用者が5日分の休暇の取得時期を指定できるようになりました。
賃金
法律では、賃金の支払い方法について明確な基準が設定されており、以下の5つの原則があります。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月払いの原則
- 一定期日払い
出典:e-GOV 法令検索「労働基準法 第二十四条(賃金の支払)」
賃金は、中間搾取を防ぎ、労働の対価が正確に労働者に渡ることを保証するため、原則として通貨で支払われ、労働者本人に直接全額が支払われなくてはなりません。
さらに、最低賃金法では最低賃金制度を設けており、都道府県ごとに設定された最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
また、時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては法定以上の割増賃金を支払うことが必要です。時間外および深夜労働で25%増、法定休日労働で35%増の割増率が適用されます。
労働基準法違反の事例と相談先
労働基準法違反の事例として、以下のものが挙げられます。
・残業代の未払い
時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を支払わない。
・有給休暇の取得拒否
労働者が取得を希望する有給休暇を、正当な理由なく認めない。
労働基準監督署は、労働基準法違反の是正を指導し、労働者の権利を守るための機関です。もし、上記のような違反、または違反を疑う対応をされた場合は、お近くの労働基準監督署に相談するようにしましょう。
まとめ
労働基準法は、過酷な労働条件から労働者を守るための法律で、労働条件の最低基準を定めています。
例えば、労働時間は1日8時間、週40時間を原則とし、時間外労働には割増賃金の支払いが必要です。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が求められます。
もし、ご自身の労働条件について疑問がある場合や違法性を感じる場合は、労働基準監督署をはじめとした専門機関に相談することをおすすめします。




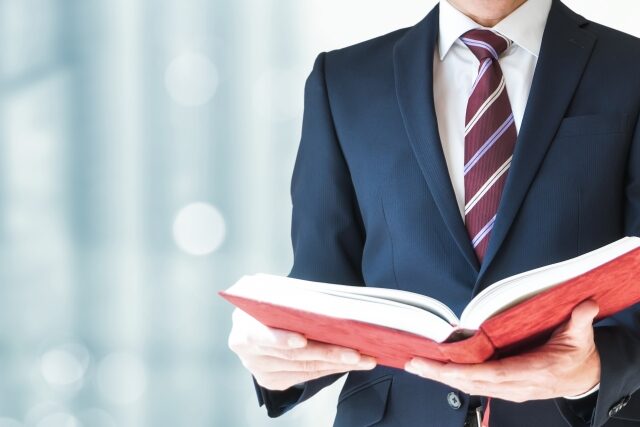
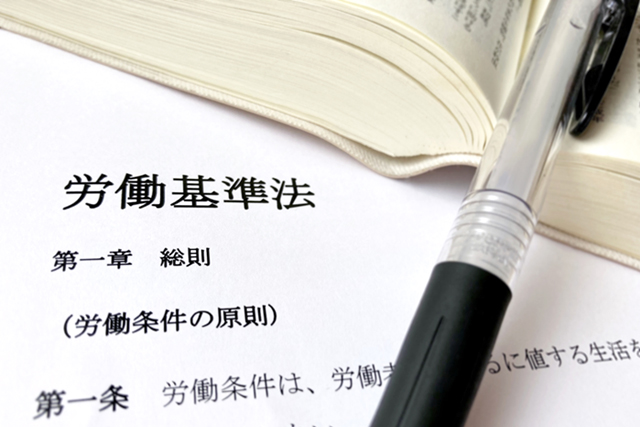
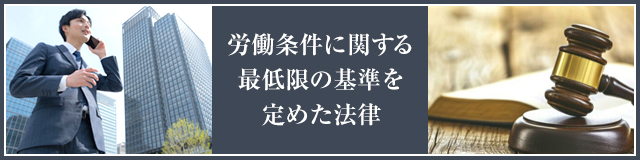









コメントを残す