働き方が多様化した現代社会では、会社に所属するのではなく、フリーランスという働き方を選ぶ方も増えています。また、会社に所属しながら副業として能力を生かして働く方も多いです。しかし、組織に所属しないフリーランスは労働基準法で保護されないため、口約束など曖昧な形で契約を結んだり、報酬の支払いが遅れたり、一方的に減額されたりするケースが起きていました。
そこで、トラブルを防ぐために2024年11月より施行されたのが「フリーランス新法」です。フリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を作るための法律です。
この記事では、フリーランス新法の概要から、個人事業主が得られる具体的なメリット、注意点、トラブルが起きた際の相談窓口まで解説します。
目次
フリーランス新法とは
フリーランス新法とは、フリーランスとして働く個人が安心して業務に従事できる環境を整備することを目的とした法律です。正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法」で、フリーランス保護新法とも呼ばれます。
フリーランス新法では、主にフリーランスを雇う法人に対して以下の義務を課しています。
【フリーランス新法の内容】
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払い期日の設定・期日内の支払い
- 受領拒否や報酬減額、買いたたきといった7つの不当行為の禁止
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 業務委託の中途解除等の事前予告・理由開示
フリーランス新法の対象者
フリーランス新法における「フリーランス」とは、主に業務委託で仕事を請け負い、かつ従業員を雇用していない事業者です。個人事業主はもちろん、従業員を雇っていない法人(一人社長)も対象に含まれます。
また、対象となる業種は問いません。ライター、カメラマン、デザイナー、コンサルタント、インストラクター、配達員、建設業者など、フリーランスとして働いているあらゆる業種が対象となります。
また、企業に雇用されている人が副業として業務委託を受ける場合も、フリーランス新法の保護対象です。
一方で、フリーランス新法では「従業員」は保護されません。法律上の従業員とは、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる」者を指します。契約上は業務委託契約を結んでいる場合でも、実態として従業員である場合、フリーランス新法ではなく、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。
フリーランス新法で個人事業主が得られるメリット
フリーランス新法の施行前に行われた、日本労働組合総連合会の調査では、フリーランスのうち半数近くの46.6%が契約にあたってトラブルを経験していました。うち、最もよく起きたトラブルは以下の通りです。
【フリーランスの契約にあたって起きたトラブルワースト5】
| 不当に低い報酬額の決定 | 28.8% |
|---|---|
| 報酬の支払いの遅延 | 25.8% |
| 一方的な仕事の取消し | 25.1% |
| 報酬の不払い・過少払い | 24.9% |
| 一方的な仕事内容の変更 | 20.2% |
出典:日本労働組合総連合会「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2024」
そこで、フリーランス新法では、労働基準法の対象外だったフリーランスが保護され、企業に勤めていた労働者と同様に適正な契約を結べるようにルールが決められています。
フリーランス新法のメリットは、以下の通りです。
取引条件が適正化される
フリーランス新法の導入により、個人事業主の取引条件が適正化されます。契約の透明性が向上することで、トラブルの防止につながり、安心して業務を遂行できるようになる点がメリットです。
フリーランス新法により、報酬の支払期日が「納品または役務提供後60日以内」に定められ、契約内容の明示が義務付けられました。報酬未払いのリスクが軽減され、フリーランスが安定して業務を行える環境が整備されます。
また、正当な理由のない報酬減額や返品、不当に低い報酬額の設定といった不公正な取引を防ぐための禁止事項も設けられており、従来の下請法や独占禁止法の範囲を超えてフリーランスの問題をカバーしています。そのため、フリーランスは公正な条件のもとで働けるようになります。
就業環境が整備される
フリーランス新法は、取引条件の適正化だけでなく、個人事業主の就業環境の向上も期待できます。ハラスメント防止がルールに定められているため、取引先が立場を利用してパワハラ・セクハラ・カスハラを行ったりすれば、罰せられます。
また、フリーランスが業務と育児・介護等と両立できるよう、雇い先に合理的配慮をすることを命じているため、育児と仕事の両立が困難な働き方を強要されません。
加えて、契約の中途解除の際には事前通知や理由開示が求められ、一方的に契約を解除されるリスクも減らせます。
より多くの人が安心してフリーランスとしてのキャリアを築くことができるようになり、個人事業主として長く働けるようになるでしょう。
個人事業主にとってフリーランス新法のデメリットはある?
フリーランス新法は、個人事業主の立場を守る目的で定められました。しかし、発注業務者側の負担が増大することにより、フリーランスへの発注控えが起こるリスクが指摘されています。
従来、口約束や簡易なやり取りで業務委託契約書を結んでいたケースでも、フリーランス新法のもとでは契約内容の明確化が義務付けられ、書面や電子データでの契約が求められます。
契約の締結に手間がかかり、管理が大変なことから、法人の規模や担当者の業務量によっては、フリーランスへの依頼を控えるケースが増える可能性もあるでしょう。
発注側がフリーランスに業務を依頼するメリットは、「手軽に発注できる」「管理コストや人件費を削減できる」などです。発注側の手間が増えることで、法人との契約や内製化に切り替える企業も出てくるでしょう。フリーランス側も、保護される分「簡単に契約できる」以外の自身の強みを持つ必要があります。
フリーランス新法で個人事業主が注意・確認するポイント
フリーランス新法は、発注側だけでなくフリーランス側も契約条件や内容を理解する必要があります。トラブルを防ぎ、安全に取引を行うためには以下のポイントを留意しておきましょう。
取引条件が明記されているか
委託事業者から業務を委託される前に、取引条件が明記されているか確認することが大切です。確認するべき記載事項は以下の通りです。
- 業務委託先および特定受託事業者の名称
- 委託契約の締結日
- 特定受託事業者が提供する給付内容
- 給付の受領または役務提供の期限
- 給付の受領または役務提供の場所
- 給付内容の検査が必要な場合の検査完了期限
- 報酬の金額および支払い期限
取引条件は、記録に残る形で残っていれば書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージなど)のどちらでもかまいません。ただし、口約束で契約するのは明確に禁止されているので、これまで口頭で契約していたクライアントには、改めて記録に残る形で取引条件を明記してもらいましょう。
支払期日はいつか
フリーランス新法では、業務委託契約において報酬の支払期日を明確に記載することが義務付けられています。発注事業者は業務完了後60日以内に報酬を支払う必要があり、可能な限り早い期日を設定するよう求められます。契約書に「○月○日支払」や「毎月○日締め、翌月○日支払」など、具体的な期日を明記されているかチェックしましょう。
再委託の場合は、「再委託であること」「元委託者の名称」「元委託業務の対価の支払期日」を明示することで、元委託者の支払日から30日以内の支払期日に設定可能です。
また、支払期日を契約で明確に定めることで、未払いリスクの低減やキャッシュフローの安定につながります。報酬の減額や一方的な変更といった禁止行為を避けるためにも、契約時に支払条件を確認し、書面で合意することが重要です。
トラブルの際にはどこに相談すればよいか
フリーランス新法では、発注者の禁止行為や違反行為に対する救済措置が整備されており、トラブルに直面した際は相談窓口を活用しましょう。主な相談先として「行政機関の窓口」や「フリーランス・トラブル110番」があります。
フリーランスが違反行為を受けた場合、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省などの行政機関に申出が可能です。状況に応じた相談先は以下の通りです。
| 取引の適正化に関する違反 | 公正取引委員会・中小企業庁 |
|---|---|
| 就業環境の整備に関する違反 | 厚生労働省 |
どちらのケースでも、オンライン窓口あるいは電話・郵送の形で公正取引委員会のWebサイトに掲載された窓口へ送れば、窓口担当者が所管する行政機関へ届けてくれます。
出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」
また、「フリーランス・トラブル110番」は、厚生労働省が委託する第二東京弁護士会によって運営されており、無料で相談ができる窓口です。必要に応じて和解のあっせんや適切な行政機関への紹介を行ってくれます。
安心して業務を行うために、トラブル発生時の対処法や相談先を事前に把握し、適切な対応をとることが重要です。
なお、個人事業主の税務に関する相談先としては「永安栄棟 公認会計士・税理士事務所」がおすすめです。完全オンラインにて、日々の記帳から決算書の作成、確定申告書の作成まで丸投げすることができます。
まとめ
フリーランス新法では、取引条件の明確化や報酬支払いの期日設定、業務委託の適正化などのルールが定められました。これまで労働基準法で守られておらず、下請法があってなおトラブルに巻き込まれるケースが多かったフリーランスにとって、働きやすい形に環境が変わると言えます。
一方で、発注者側にとっては管理コストが増えるため、簡単に契約できるという強みがなくなるという点では、フリーランスにとってデメリットです。発注者側でなく、業務委託を受けるフリーランス側も、フリーランス新法の内容を理解し、契約内容を確認するとともに、トラブル時の相談窓口を知っておくことが重要です。




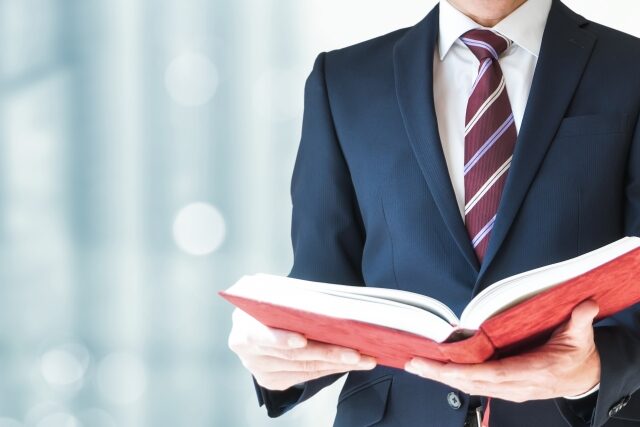








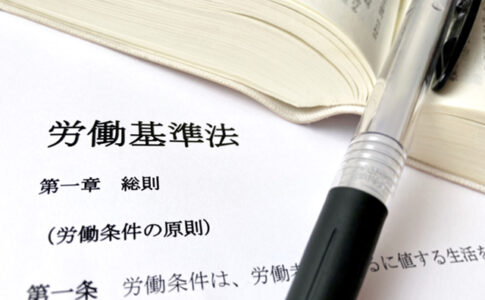


コメントを残す